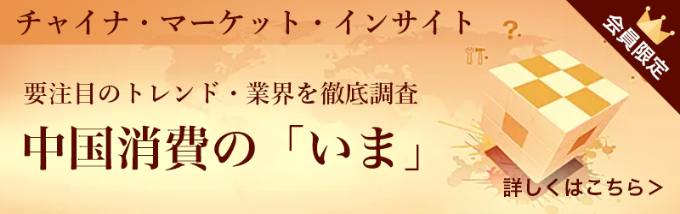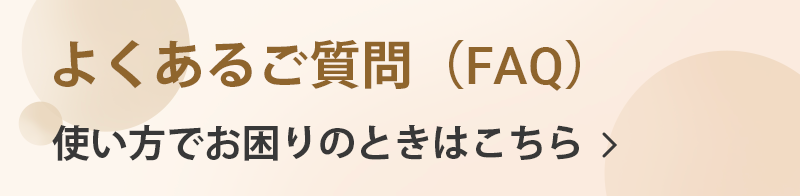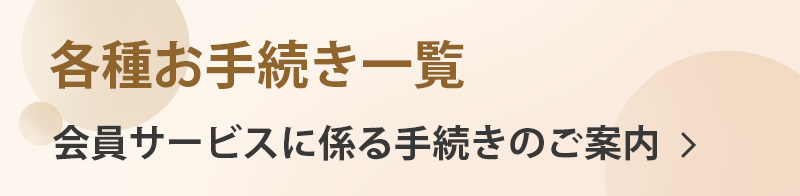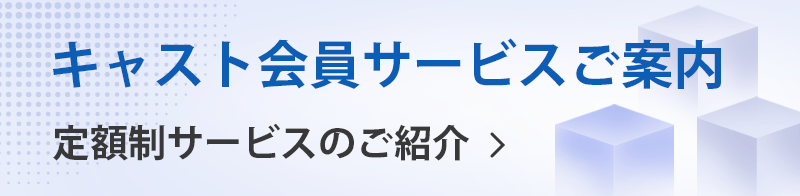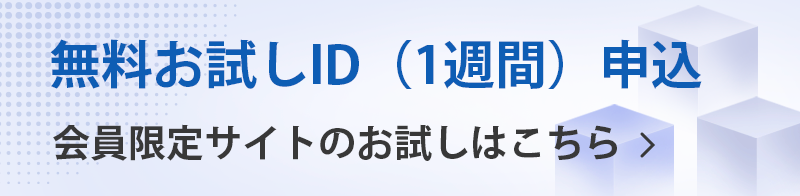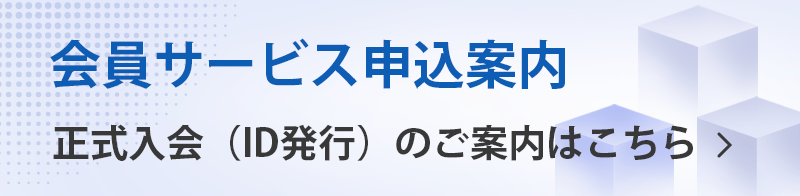~「仕組み」と「人」と「場」をつくる~人事と組織のマネジメントーー第36回 評価する「基準」をマネジメントする(その1)
株式会社 J&G HRアドバイザリー
代表取締役社長 篠崎正芳
本質解は、やはり、評価の「基準」にある
日本人でも外国人でも人は仕事をする限り、その成果や貢献度を適切に評価してもらいたいと考え、経営側もそれらを適切に評価したいと考えます。しかし、現実は、どんな組織でも評価に不満を持っている人は存在します。そのため、「適切な評価」は解決が難しい“永遠の課題”と認識されてしまい、本質的な解決をするための行動が十分にとられていない実態に今まで何度も遭遇し、解決の支援を続けてきました。
長年の問題解決の経験をとおして改めて言えることは、評価に不満を抱く社員の数をゼロにすることは至難の業ですが、少なくし、健全なマネジメントを目指すことは十分可能なのです。そのためには、評価の「基準」を明確にしなければいけません。何がどれだけ達成できれば、あるいは、何がどれだけ発揮できればどのような評価になるのかを明確にしなければいけないのです。企業によって、この「何」にあたることについての概念範囲や言葉には違いがありますが、汎用性のある表現では、「目標」と「行動・能力」の2種類に集約できます。
固定的な基準V.S.流動的な基準
「行動・能力」は、会社の戦略やビジネスモデルが大きく変化しない限り、期待している内容を明確に定義すれば、それを基準として一定期間(例・数年)は固定化できる性質を持ち備えています。定義をする人は通常、結成されたプロジェクトの構成メンバーになる人事部門と事業部門の人で、彼らがある時期に定義のための作業を集中的に行うことになります。その際には、個々の役割や業務の特性を十分踏まえて「いかに肌感覚に合う明確な定義ができるか」が最大の課題であり、最重要ポイントとなります。
一方、「目標」の概念には、「結果」だけの場合と、「結果」と「手段・活動」を含む場合の2つのケースがあります。いずれのケースでも、「目標」は、毎年、各職場で上司と部下が話しあって確認しあわなければいけません。つまり、「目標」はその設定に関わる全員の「思考と行動」に深く連動しているのです。会社として一度定義すれば「基準」として固定化できる「行動・能力」とくらべて、「目標」は都度、人と人が直接的に対話を繰り返さなければいけないことから流動的であるといえます。関わる人のコミュニケーション能力が目標の明確性や納得性に大きな影響を与えることになるのです。
日本企業で目標管理がうまく機能しにくいワケは?
「目標管理制度を始めたが、なかなかうまく機能していない」という残念な現象が少なからずの日本企業で起きてしまっています。なぜこのようなことが起きてしまうのでしょうか?
自然体の経営感覚が薄れている
例えば、資産家でない普通の人が成し遂げたいことがあり、自分のお金で会社を作り社員を雇用したとき、全社員を定年まで雇用することを約束する経営者はまずいないでしょう。会社業績については、もちろん右肩上がりの成長を目指しますが、「現実は良い時もあれば悪い時もある。悪い時にも耐えることができるマネジメントを整えておく」と考えるのが普通のリスク感覚です。さらに、業績向上に向けて、毎年の目標を組織と個人において明確にし、その達成度合いを適切に評価して、優秀な社員、成長見込みのある社員、成長見込みのない社員など、人材を見極めることになります。その結果、役職、役割に見合った報酬も決めることになります。また、このプロセスの中で、社員ひとりひとりの成長を期待し、良いことを褒めたり、改善すべき点を叱ったりすることを繰り返すことにもなりますが、これら一連の行動はまさに“自然体”の経営感覚にもとづいた経営行為なのです。
しかし、残念なことに、いま多くの日本企業では、この“自然体”が失われてしまっているようです。バブル崩壊前の成長期に培われた「差がつかない平等」感覚や「会社と社員のもちつもたれつ」感覚が、バブル崩壊後20年経過した先行き不透明な現在でも、迷いを伴いながら無意識のうちに深く残っているようです。このような感覚の下では、目標管理を始めても社員が本気になれませんし、結果、本来の目標管理がうまく機能しなくなっても仕方ないでしょう。欧米企業、アジア企業と戦って生き残っていくいためには、まずは、自然体の経営感覚を取り戻すことが大切です。
目標達成度“以外”で評価が決まる
多くの日本企業での評価実務の実態は、目標達成度“以外”の「要素」で評価が決まっていることです。この「要素」が明確に定義された「行動・能力」であれば問題ないのですが、現実はそうではありません。この「要素」は評価者の主観や感覚に基づいた曖昧なものであることが多く、説明が大変難しいのです。さらに、この「要素」の評価が最終評価結果に与える比率が高くなりがちなことが問題を深刻にしているともいえます。
折角、目標管理制度を導入しても、これでは、台無しです。目標設定シートに記述した内容や達成度が結果的に軽視されてしまうのであれば、上司、部下の面談で「形」だけを整えるプロセスは時間のムダと感じる人が増えても仕方ありません。その結果、目標を真剣に考えることに価値を見出すことができる社員が減り、目標管理は自ずと機能停止し、社員の経営感覚が薄らいでしまうのは当然の帰結といえます。
「究極の“勘”」の妥当性が高い
大変興味深いのは、日本企業での最終評価結果の妥当性が案外高いことです。日本企業で評価が高い人は、社内の市場原理が働き、人から信頼され任される仕事が増え忙しくなります。存在感も高まります。そして、役割が大きくなり役職も高くなるので、周囲の人からも客観的に認知されやすいのです。周囲の人に「えっ、なんであの人が評価されているの?」と本気で疑問を抱かせてしまうような人は少なく、むしろ、「やっぱりそうだよね・・・」と認識されることの方が多いのです。
ですから、仮に不満や疑問を感じる人がいたとしても、その人は雰囲気的に文句を言いにくくなります。また、文句を言うことで「変なヤツ」とレッテルを貼られるリスクもあるので、今後のサラリーマン人生を考えて、その時の不満や疑問を消去してしまうのです。
つまり、多くの日本企業では、非明示的で説明が難しい「要素」で社員を評価しているのですが、不思議なことに、評価結果の妥当性が高く、社員に受け入れられてしまっている奇妙な現象が起きているのです。この背景には、日本人同士の高い同質性が感覚的に共感、同感できる「言わずもがな」の幅を広げていることは言うまでもありませんが、世界でも珍しく日本で「究極の“勘”」によるマネジメントがうまく機能してしまうことが、皮肉なことに、目標管理の機能に障害を与えてしまうことになってしまうのです。
次回は、海外拠点で評価する「基準」をマネジメントするために、日本人マネジメントが新しく習慣として身につけなければならない本質的で筋のよい行動についてお話します。





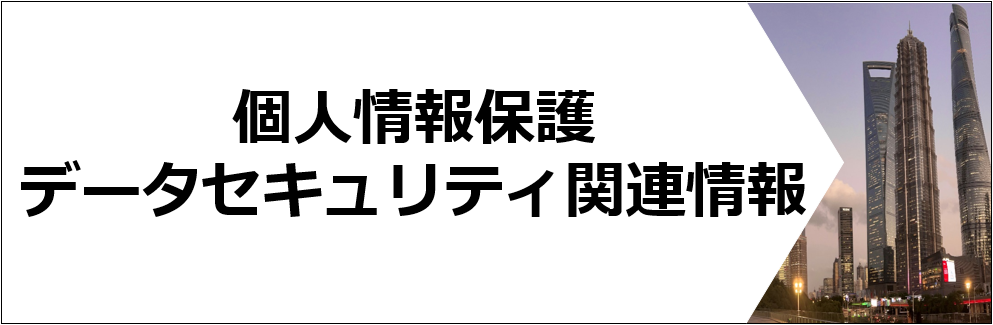
![]RDVJ6`_IQ[2NVMSN_B50RR.png](https://castglobal-china.biz/s3/new/image/e9015a506fd3e04ef794b76ccfa5b063.png)